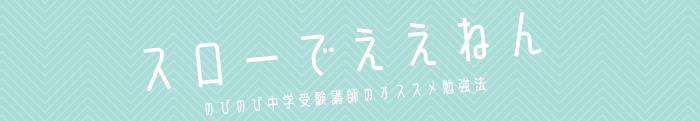※本記事はADを含みます。

うちの子は計算問題が苦手みたい。計算スピードも遅いし。算数の成績も悪いし、中学受験本番までになんとかしないと・・・。
このような疑問にお答えします。
まず結論から言うと、算数が得意な子は自然と計算技術を身につけています。学力の高い子は地頭も良く、計算のやり方に関しても常に貪欲。「こうすればもっと早く解ける」と計算技術を自分で編み出しています。
もちろん塾のテキストでも中学受験の計算技術を習います。しかし、学校で教わる計算は筆算中心の基本的な計算技術。中学受験の計算技術とはだいぶ乖離しており、算数が苦手な子はここでふるい落とされてしまいます。
たとえば、中学受験で代表的な逆算の計算を見てみましょう。
A 逆算の場合は、まず□のあるかたまりから求めるのが常識です。□+1.2を大きな□で囲ってやる。となれば、□×5=9となります。となれば、□には1.8が入りますね。となれば、□+1.2=1.8。よって、□は0.6と求まるわけです。
塾でも習いますが、算数が得意な子は自然と身につけている印象があります。インド式計算技術など、教わらなくては身につかないものもあります。
一方、小学校では筆算で丁寧に解くやり方を学びます。小学校で習う計算技術と中学受験の計算技術はだいぶ乖離しています。ここで苦手意識が生まれます。
算数が苦手なお子さんは、まず計算力がありません。計算力が向上すると、算数に興味も生まれて、自然と勉強時間も増えてくる。正のスパイラルに入っていけます。
中学受験算数を分解すると、①計算力、②解法、③解法のロジック、この3点に分解できます。中でも土台となるのは①計算力。中堅~上位校を目指すお子さんでも、小6夏休み前には十分な計算力がほしいです。
残念ながら、小6の夏休みまでくると大手進学塾のプログラムではカバーできません。小5であれば、計算演習プリントなどまだ手厚くフォローしてくれますが、小6生ともなれば演習中心の授業となります。
次のような特徴がある子、
・模試の大問1における計算問題で全問正解できない。
・計算問題を解くのに時間がかかりすぎる。
上記に当てはまるお子さんは要チェックです。家庭教師の先生にお願いして特訓するか、保護者の方が中学受験の計算を教えるしかありません。お子さんの計算力にお悩みの方はぜひご一読ください。
この記事を書いている人:集団塾、個別塾など中学受験講師として経験を積む。現在は、社会人のプロ中学受験講師。読み書き障害など、発達障害を抱えたお子さんにも独自なメソッドで学力を伸ばすことに日々情熱を燃やしております。
【比較】計算が苦手な子と得意な子
算数の偏差値が50以下、いや45以下のお子さんは計算力に間違いなく問題を抱えていると判断していでしょう。たとえば、大手進学塾では、次の問題は小3レベル。
計算が苦手な子
中学受験の計算力が身についていないお子さんの場合は、
計算式に書かれている順序通りに、まず8×32を筆算で計算します。6年生は、マス目入りのノートなど使いません。そのため筆算がずれてしまう。ここで計算ミス。
その計算ミスが響いて、×125の計算を「諦めて」しまいます。
計算が得意な子
一方で、中学受験の計算力が身についている子の場合は、
掛け算は順序をいれかえてもよいので、8×125×32と計算します。8×125は1000であることは常識です。
1000×32で、32000と一瞬で答えを出す。正確には掛け算の交換法則といいますが、ともかく使いこなせればOKです。
算数が苦手なお子さんは、2ケタ×1ケタの掛け算の暗算もスムーズにいきません。たとえば、
計算が苦手なお子さんは「ええっと、8×6は48だから、次に8×50をして~」と時間がかかる。たびたび間違える。
「下から計算」しています。素早く正確に計算するには、「上から計算」しなくてはいけません。
「8×50は400で、それに8×6の48を足す。448だよね」としたほうが正確で早く計算できますよね。
計算技術は毎日3時間、2週間みっちりと教える
確かに生まれつき計算センスがあるのは事実です。得意な子は、教わらずとも自分で計算技術を発見しているわけです。
そうでない子には、中学受験の計算技術として「誰か」が教えなくてはいけません。
計算問題は毎日取り組むもの。週1の大手進学塾では不可能。当然、自宅学習しかありません。
大手進学塾では、小5、6年から授業にセカンドが追加。演習授業として算数の授業は週2になりますが、このセカンドでは演習が中心。計算技術を教えることはありません。
もちろんプロ家庭教師の先生にお願いするのも一つですが、どうしても費用が高くなります。そんな場合は、学生家庭教師の先生。
近場の大学の生協さんにご連絡されてみるのもオススメです。お住いの近くの学生さんであれば、毎日自宅に通いやすいと思います。
必要なことは、毎日3時間、2週間みっちりと教えてもらうこと。毎日続けることです。家庭教師委託会社を通さずに、個人契約となりますので、その点はご注意ください。
毎日2時間×3週間でも構いません。42時間。時給千円としても、1000×42=4万2千円。中学受験の計算問題が解けるようになれば、コスパは良いです。
計算力が身につくオススメ教材をご紹介!
どのように中学受験の計算技術を教えるのかという点をお話しします。
私がお勧めする本は、石井俊全氏著『中学入試計算名人免許皆伝』(東京出版)です。
こちらの本は、中学受験で身につけるべき計算方法のノウハウを丁寧に説明されております。付録の計算カード192枚も魅力的です。単語帖の暗記カード。本書のサイズも大判サイズ、大きな字。見やすい。使いやすい参考書です。
まずはこの著書の内容を理解する。使いこなせるようになれば、十分に中学受験算数の計算力の土台は身につけられます。周りのお子さんを追いかけ、追い越しましょう!
保護者の方、あるいは学生家庭教師の先生が、お子さんと一緒に取り組めばOKです。
ですが、『中学入試計算名人免許皆伝』は計算技術の参考書です。アウトプット用の、計算問題集も並行して進めてください。
オススメ問題集は、『中学入試 でる順過去問 計算 合格への920問』(旺文社)あるいは『小6計算練習800題 』(桐杏学園出版)。少し難しければ、『小5計算練習800題』(桐杏学園出版)から始められても構いません。
まとめ
計算力は、中学受験算数における土台。計算問題は正確に、素早く全問正解しているかどうかを確認していただきたいです。もし計算ミスが多く、時間がかかる場合。一日でも早く改善が必要です。
大学生のアルバイト家庭教師の先生に、今回ご紹介した参考書などで毎日3時間2週間。みっちりと指導する。時給千円で依頼したとしても、4万2千円です。
十分な中学受験の計算力が身につかないまま、受験当日を迎えるような事態だけは絶対に避けなくてはいけません。
学習ルートとしては、6年生の夏休みまでに『中学入試計算名人免許皆伝』で計算技術を習得する。問題集は『でる順過去問 計算 合格への920問』をこなす。あるいは、塾で使用されている計算問題集をご利用ください。
もし『中学入試計算名人免許皆伝』が難しい場合は、最後の手段です。学習漫画に頼りましょう。ドラえもんシリーズは、中学受験大手の四谷大塚さんが監修されていて、中学受験向きの学習漫画です。
「ドラえもんの算数おもしろ攻略 計算がはやくできる」(小学館)もその一つ。こちらで計算への苦手意識を少しでもなくし、計算力向上を図りましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。